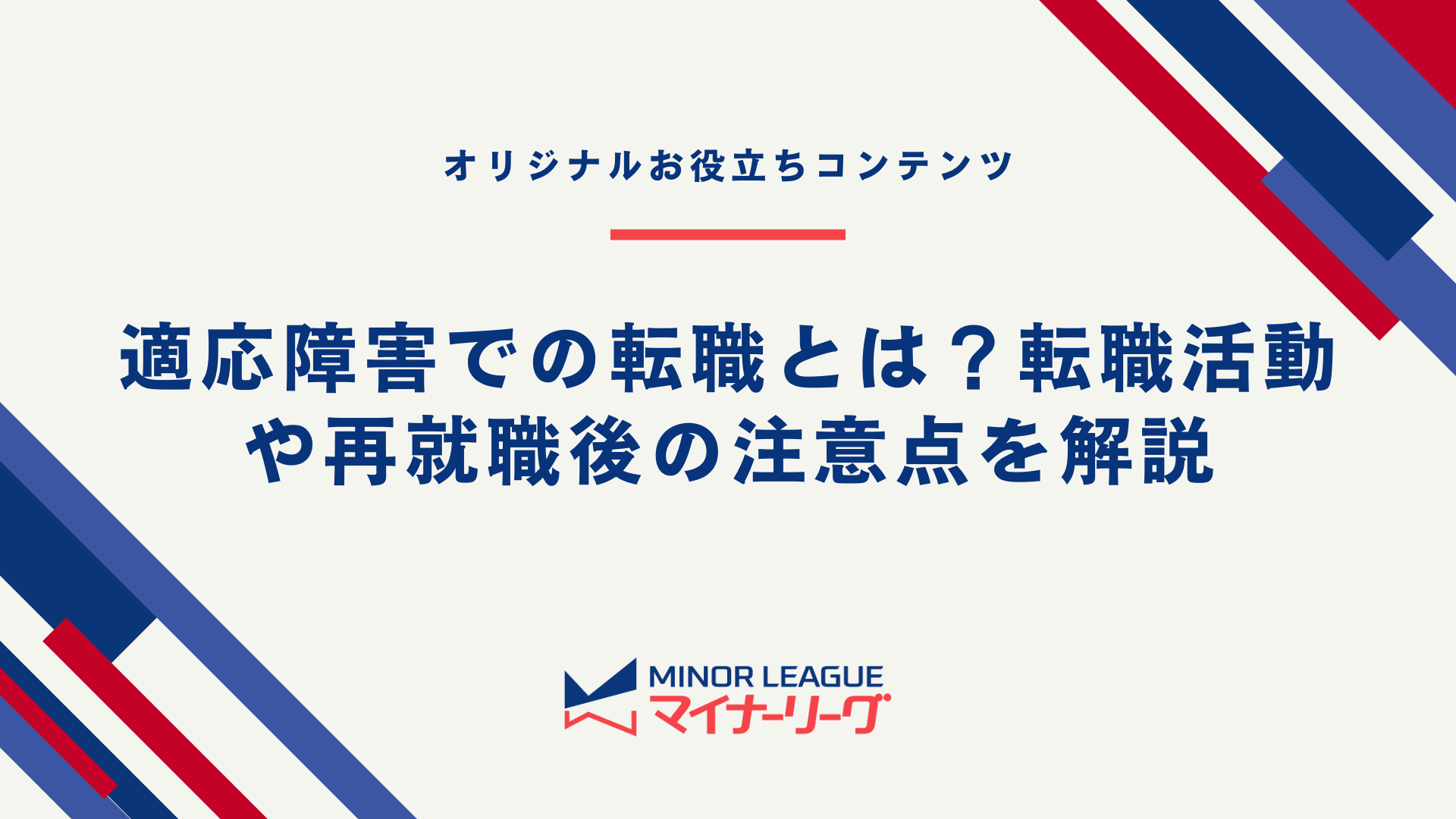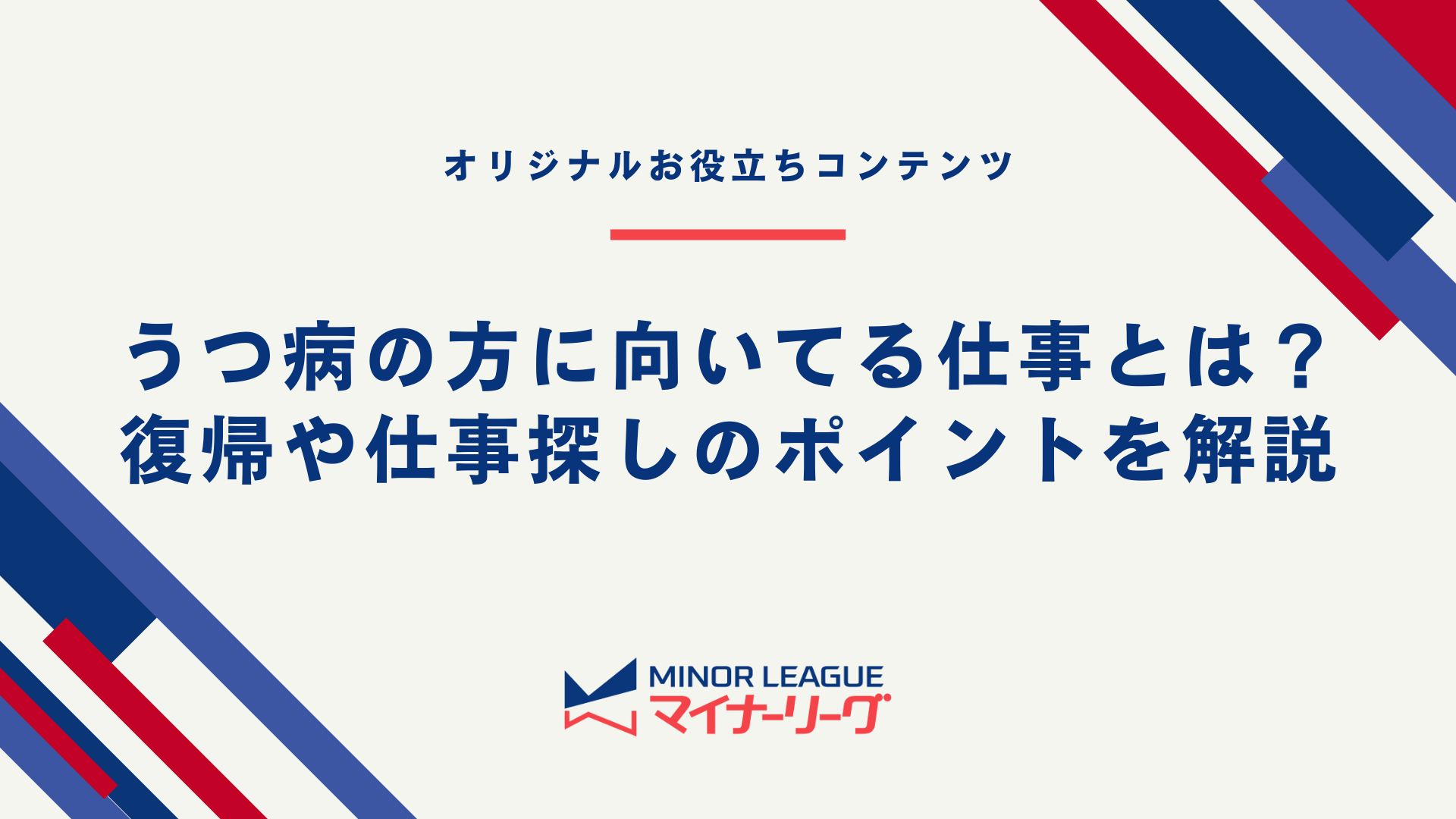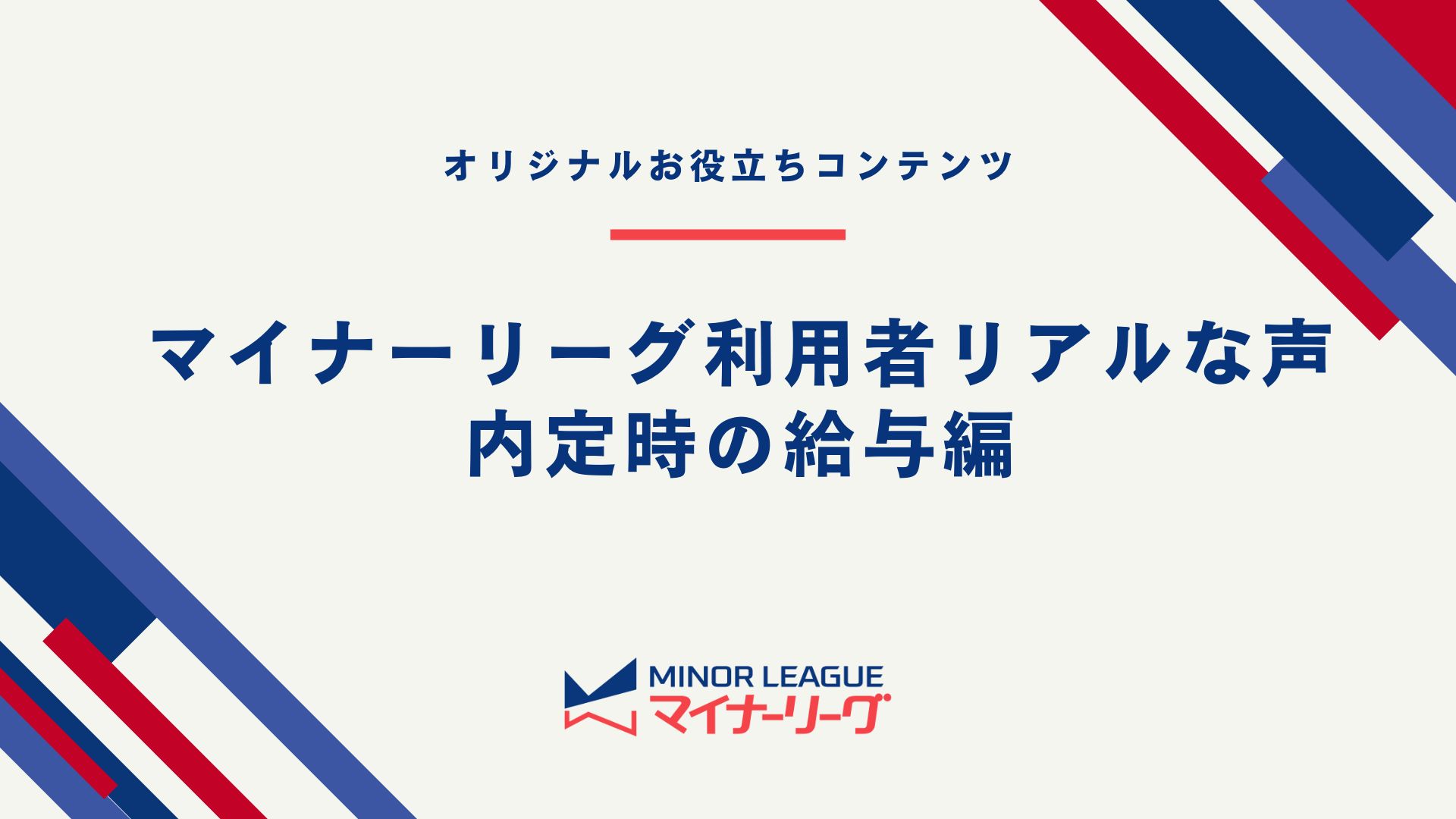「また不採用になってしまった…。一体どこがダメだったんだろう?」
障害者雇用で面接に落ちてしまい、悩んだ経験はありませんか?
自分のどこを改善すれば良いのか、途方に暮れてしまうことがあります。そのようなときに応募した企業に、なぜ自分がダメだったのか聞きたくなる気持ちが出るのは当然のことでしょう。
では実際に、応募先企業に不採用理由を問い合わせてもよいものなのでしょうか?
この記事では、不採用になった理由を探る方法や、考えられる不採用の理由と対策などを解説します。
マイナーリーグに登録すると
就活資料のダウンロードが可能!










目次
企業に問い合わせても不採用の理由は詳しく教えてくれない
結論から言うと、不採用理由の問い合わせはおすすめしません。ほとんどの場合、具体的な理由があっても伝えてはもらえず、相手方を困らせるだけになってしまうためです。
企業が不採用理由を具体的に教えてくれないのには、いくつかの理由が考えられます。
- トラブル回避:具体的な理由を伝えると、応募者から反論や法的措置などのトラブルに発展する可能性があるため、リスク回避のために詳細な説明を避けるケースが多いです。
- 企業イメージ:採用活動は企業の顔であり、不採用理由を具体的に説明することで、企業のイメージを損なう可能性も考えられます。
- 選考基準の機密性:企業独自の採用基準や評価基準は、企業の貴重な資産であるため、外部に漏らしたくないという考えも働きます。
それでも不採用になった原因を探る方法
不採用理由が分からないと、今後の就職活動に活かすことができません。しかし、諦める必要はありません。いくつか具体的な方法を試してみましょう。
模擬面接
模擬面接を行い、第三者からアドバイスをもらうことをおすすめします。
「自分では上手く伝えているつもりだったのに…」と思っていても、うまく伝わっていなかったり、意図と違う内容で伝わっている可能性があります。
模擬面接を行うことで、あなたの言葉遣いや態度を客観的に評価してもらいましょう。
また、想定外の質問にどう答えるか、事前に練習することも可能です。
模擬面接は、就労移行支援などを利用されている場合はその事業所で受けられることが多いですし、それ以外でもハローワークや障害者就業・生活支援センター、地域の障害者就労支援センターなどでも受けられます。
参考:
東京ハローワーク 就活支援メニュー
障害者就業・生活支援センターについて
想定問答集の作成
面接での質問と回答を書き出し、改めて自身で見直すことで、改善点を見つけ出すことができます。
「もっと具体的に自分の強みをアピールできたかもしれない…」という項目があれば、想定問答集を書き直してみましょう。
文字にすることで、自分の伝え方が客観的に評価できます。また、回答の不足している点や、改善すべき点を明確にすることができます。
想定問答集についてはこちらの記事も参考にしてください。
支援者の面接同席
就労移行支援などの支援機関を利用している方は、支援者に面接同席をしてもらうことも一つの手段です。
支援者に同席してもらうと、第三者の視点から面接の様子を観察することができるので、具体的なフィードバックを提供してもらえるでしょう。
「あの時、もっとこうすればよかったんじゃないかな?」といった、支援者からの客観的な意見をもらうことで、今後の面接に活かすための貴重なヒントになります。
また、支援者に同席してもらうことで、面接のフィードバックをもらえるほか、自身としても安心して面接に臨めたり、うまく伝えられないことを支援者が補足してくれるなどのメリットもあります。
参考:支援者の面接同席について、企業側の認識
支援者の同席について面接官側がどう捉えるかは、企業によって異なります。
「ぜひ支援者に同席してもらってください」という会社もあれば、「どちらでも良いですよ」あるいは「同席不可」という会社もあります。
支援者に同席してもらうことで、「頼れる支援者の方がいて、入社後も安心だな」とポジティブに受け止められることもあれば、「支援者が一緒じゃないと一人で面接に来られないのかな」とネガティブに受け止められることもあります。
安定を重視するのか/自立性を重視するのか、など職場の方針によっても受け止めが異なります。
総合的に考えて、面接に同席してもらう方がメリットが大きいかどうか、支援者の方と相談すると良いでしょう。
障害者雇用における不採用の主な理由
障害者雇用で不採用になる主な理由としては、以下のようなものが考えられます。
就労に向けた準備が整っていないと判断された
障害者雇用において、能力やスキル以前に、体調管理等の「就労準備」が整っているかどうかを重視する企業は非常に多いです。
具体的には、生活リズムが整っていないように感じられた、服薬管理やストレス管理などが自己管理できていないと判断された、障害に対する自己理解が不十分だと感じられた、などです。
確かに自分はまだ就労に向けた準備が整っていない、と感じる場合には根本的な解決が必要です。就労移行支援などの利用もご検討ください。
参考:Kaienの就労移行支援プログラム
能力がミスマッチだと判断された
求めているスキルを満たしていない(スキルや経験が足りない)と判断されたかもしれません。実際にスキル・経験が基準を満たしていないのであれば、それは仕方ないことなので自己研鑽してスキルアップするなり、応募先を再度検討するなりの対処が必要です。
あるいはスキルが高すぎてミスマッチと判断された可能性もあります。その場合は応募すべき求人がミスマッチだったかもしれません。いずれにせよ今の自分に見合ったちょうどよい求人を選定しましょう。
一方で、自分は十分スキルを満たしているはずなのに、そう判断されたという印象なのであれば、面接練習や想定問答集のブラッシュアップをして自己PRを磨き上げましょう。
ほしい人材とのイメージが異なっていた
具体的な配属先の部署やチームが想定されている場合には、この判断基準により不採用となることは多いようです。
具体的には職場のバランスを考慮したうえでほしい人材と年齢層が異なっていた、や「上司となるの○○さんとの相性が合わないタイプだな」など、そういった具体的な配属を検討したうえでの判断です。
こういった不採用理由なのであれば、求職者側は改善すべき余地はありません。「そもそも相性が合わなかった」と割り切って考える方が良いでしょう。合わないところに採用されても、のちのち苦労するだけです。企業はたくさんあるので気持ちを切り替えて自分に合う場所を探しに行きましょう。
相対的に判断して、よりよい人がいた
おそらくこれは最も多い、不採用理由なのではないでしょうか。採用基準を満たしている応募者が複数名いた場合には、その中の1名を選ばざるをえません。
急ぎで複数名の採用をしたい場合には、多少スキルが低くても採用されることもありますし、逆にある程度充足している、あるいはたくさん候補が集まった場合には厳選して採用する場合もあり、こればかりは運とタイミングの問題です。
まとめ
就職活動において不採用の理由を振り返りして、次に生かすことは重要なことですが、応募先の企業が具体的な不採用理由を教えてくれることは少ないでしょう。
しかし、模擬面接や想定問答集の作成、支援者の同席など、様々な方法により自分の課題を見つけ出し、改善していくことは可能です。
一方で、不採用の理由が自分にはどうしようもない、「運とタイミング」としか言いようがない理由である場合もあります。できる範囲での反省・改善と、気持ちの切り替えの両方が大事です。1回不採用だったからと自信を失ったり諦めたりせず、できる対策を取りながら、自分に合う就職先を探していきましょう。
求人サイト「マイナーリーグ」では、あなたのスキルや経験に合った仕事が見つかるはずです。ぜひ、求人情報をチェックしてみてください。
あなたの強みや専門性を活かせる
求人サイトマイナーリーグ